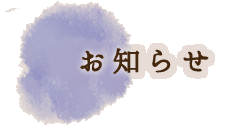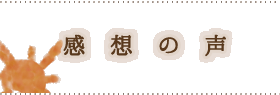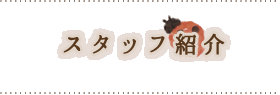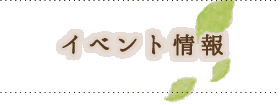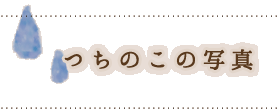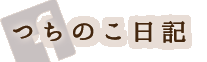
【自然保育所 つちのこ 事故の報告とお詫び】
先月、2月24日原山市民公園にて行われた、自然保育所つちのこの一般向け親子参加イベントにて大きな事故が発生してしまいました。
この日は、大人も本気のかまくら作り と題し、大人も子供も力を合わせて、大きなかまくらを作ろうというイベントでした。 朝10時に集合した総勢15組程の親子で、自己紹介やイベントの趣旨・一日の流れなどを説明した後、かまくら作りが始まりました。
お昼前に穴の大きさが、高さ1メートル・幅2~3メートル、奥行2メートル程になり、 これで完成とし、銘々が好きな場所でお弁当を食べ始めました。この時、かまくらの周囲で食べていた参加者が数組、中で食べていた参加者が3人いました。
そして、その状態でかまくらが崩れました。
中にいた3人は、崩れた雪(氷)の下敷きになってしまいました。周囲に多くの参加者がいたため、すぐに掘り出されたのですが、1人の大人は背骨を2か所骨折する大怪我を負い 救急車で搬送され入院となりました(その後、手術が行われ現在リハビリ治療をされています)
あとの2人は子供で、幸い怪我なく救出されたのですが、直後は恐怖で泣き叫ぶ状態でした。
後でわかったことですが、かまくらが崩れる直前、上に登った子供が2人いたようでした。 登った直後に崩れてしまった様なのですが、大勢の大人がいて、誰一人子供たちの行動に気付いていませんでした。かまくらの中に人がいる状態で、上に登ることの危険について明確なインフォメーションや危機感の共有もありませんでした。
怪我をされてしまった方はもちろん、参加してくださった全ての方に恐ろしい思いを強いてしまいました。 私たちの、危機管理の甘さや認識の弱さの積み重ねが今回の事故を引き起こしてしまいました。
本当に、本当に申し訳ありません。
怪我をされた方、心に傷を負ってしまった方の、一日も早い回復を祈っています。
今回起こってしまった事態について、関係者それぞれが、自分を責め、自身の甘さや弱さを自分に突き付け、自分を追い詰め、自分を裁くようにして、事故と向き合い、背負っていこうとしています。(怖い、恐ろしい、申し訳ない・・で終わらせてはいけない。
逃げる訳にはいかない。
それぞれが自らの思いで向かっています)
今回の事故について、徹底的に問題点を洗い出し精査していかなければならないと思っています。
近しい関係者で、ミーティングを行いました。以下に内容の要約を記します。
●“かまくら”を作ることについての、注意点や危険性を共通認識として持っていなかった(危険への意識は個々それぞれの感覚に任されていた)
(例:かまくらの形状、大きさ、間口の広さ、雪の状態、天候・気温による変化、等)
→・“かまくら”について、事前にしっかりと学びハザード(怪我や事故にしか繋がらない要因)を見極め、スタッフ間の共有、事前の参加者への情報の提供、安全への注意喚起を行う (今回に限らず様々な場面で同じことが言える。自分たちの持つスキルでは難しい、分からないことに関しては専門家や知識、経験を持つ方、警察などへの協力や助言を求めること。自分たちの力を過信しない)
・スタッフや参加者それぞれが、その場で感じた危険への認識が、流されることなく伝わる体制を整える。(誰に伝えればいいのか、伝えられた側は個人の感覚で判断せず、チームで協議し対応策を決める等)
●見守る大人の意識の薄さ(親子参加、イベントの場合の注意点、日々の保育との違いを踏まえて)
◇親子参加、イベントの際に起こりやすい大人と子どもの心理
<大人>
・大勢の大人がいるから、誰かがみているだろうという感覚⇔親子参加だから、子供はその親がみるものという感覚
・親同士の交流もしたい(子育ての悩みの共有や、新しい仲間との出会い等)
・その場で感じることがあっても、他の人は誰も思ってはいなのではないか?自分だけならまぁいいかと流して周りに合わせてしまう(その逆。一人が何かを言っていても、誰も反応しないから、別にいいんじゃないかと受け取ろうとしない、流してしまう)
・子供の自由意志にブレーキをかけられない(判断基準が曖昧になる)等
<子供>
・自己抑制がききにくくなる(開放的(気持ちや環境的要因)、友達との関係、人の多さ等)
・刺激の多さ、なんでも真似したい、やってみたい!と思う気持ち
・明確な歯止めがないと、何をやってもよいと判断してしまう
・大人の行動を見て、それはやっていいことと捉える ・大人に干渉されたくないという思い(特に年齢が高くなると)等
→イベントでは、集団心理が働く。大勢の人がいると、見守る目は多いが逆に落としてしまう点、無責任さも増える。
活動の目的の中に、自分の子供だけでなく皆で子供をみあおう(自分や家庭だけで子育てを頑張るのではなく、皆で育ちあおう)といった部分もあるが、イベントという場で安全管理という面とあわせると難しい? それもイベントの目的の一つに置くならば、全体をみる責任者、範囲を決めてその場をみる責任者の存在は不可欠 参加者への事前の、注意事項、安全への意識付け等の説明が行われなかった(そもそも説明できるだけの安全対策を講じていなかった)
イベントとしては無保険であった。(団体が加入している保険でカバーできることさえ認識していなかった) 参加者の人数、連絡先などを把握していなかった。
◇日々の保育のなかで
・それぞれの感覚で取り組むことが多かった危機管理、リスクマネジメントの体制を見直し、スタッフ間で共有する
・何でも危ない(又は大丈夫)と、勝手に判断するのではなく、一つ一つのリスク(放置しておくと怪我につながる可能性のある要因)について、しっかりと洗い出し、どこまでが子供に必要なリスク(学びのリスク)なのか、
どこからがハザード(怪我や事故にしか繋がらない要因)なのか、という判断をしっかり持って、保育に取り組む。
又、学びのリスクに関しては見守りの体制や方法、関わり方などによって、リスクを軽減する。等
*見守る大人の無責任さ。という問題については、場所や環境を選ばず大きな事故に発展する可能性が高いと懸念されます(もちろん室内で起こる事故もあります)
子供に関わる大人は誰もが留意しなければならない点だと思っています
●見逃されていたリスク
事故当日、一日の中で存在していたリスクを、ミーティング参加者それぞれが思い出せるだけ思い出して書き出しました。
一人でも20~30箇所以上のリスクを認識していたことが分かりました。その後、話し合いを行い、今回は事故や怪我にはならなかったけれどその可能性があったリスク要因がたくさん存在していたことがわかりました (例:道具の管理、駐車場の行き来、生垣の後ろの高い段差、凍ったコンクリートの階段等々)
これらのリスクをどう捉え、評価し安全管理に繋げていくかが今後の大きな課題です
<思い>
自然は怖い。危険はいつも隣り合わせ。
安全管理・危険と体験からの学び・挑戦する心・冒険心満足度・・・
そのラインを見極めるのはとても難しい。。 正解はない。マニュアルもない・・・
そしてそれら常に変化するし、これだけやっていれば100%大丈夫といった方法もない・・・
今回の事故を起こしてしまったうえで、なおその道を行くのには、とても勇気がいる・・・
でも、、 自分の意志で自由に考え行動し、仲間と関わりながら遊び学び、きらきらと生きる子どもたちの姿を見ていると、もうやめよう。。。とは、言えなくなる・・・
子供たちは、いつでも真っすぐ一生懸命に生きている。
今後どう進んで行くことが、子どもたちの幸せに繋がるのか・・・・・正直わかりません。
私たちはどこまでいっても、自然の中で生かされている存在です。
怖いからと自然を排除したり関りを持たずに生きていくことはできません。
ならば。。もう一度、まっ正面から受け入れていきたい。。そんな思いでいます
しかし、今回の事故は上記からもわかる通り、天災ではなく人災であったと受け止めています。
大きな怪我をされた方、関わってくださった全ての方、
事故を未然に防げず、辛い思いをさせてしまい、本当に、本当に申し訳ありませんでした。 自然保育所つちのこ 中田綾乃